用語集
夜空では、暗黒星雲は星の数の少ない暗い領域として認識されます。これは,暗黒星雲が背景の星の光を散乱・吸収しているためです(減光)。そこで、暗黒星雲を定量的に探る方法の一つに、星の数を数えて減光量を調べる「スターカウント法」があります。
1923年,Max Wolfは暗黒星雲およびその近傍の領域に対してスターカウントを行い、暗黒星雲が引き起こす減光と暗黒星雲までの距離を定量する方法を提案しました。これは特にウォルフ図法(Wolf diagram method)と呼ばれ、減光量の分布や暗黒星雲の距離を求める手法として今日まで広く用いられています。減光を受けていない領域での星数密度(単位立体角当たりの星の数)、減光を受けている暗黒星雲での星数密度、および星数密度の等級に対する傾きbを測定すれば、暗黒星雲による減光量を求めることができます。
暗黒星雲の背景にある星から来る光は、視線上にあるダストによって吸収、散乱を受けます。つまり、視線上でのダストの量が増えるとその向こう側から来る光は弱まります。これを星間減光または星間吸収といいます。
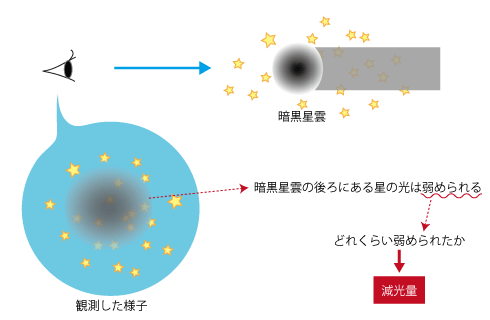
ダストの性質が同じであれば、同じ量のダストを抜けるごとに星間減光は同じ割合で増えます。このことから、星間減光の量はダストによって暗くなる等級を用いて表します。観測する波長によって星間減光量の数値自体は変わってきます。
宇宙空間で星間減光が起こるときには、光(電磁波)の波長によってその強さが異なり、一般に波長の短い(すなわち青い)光ほど強い星間減光を受けます。すると星間物質を通り抜けてきた光は赤い光(相対的に長波長)に偏り、見かけ上赤くなります。これを星間赤化とよびます。これは、星間物質を構成しているダストやガスの粒子の大きさより波長が短いものが選択的に吸収されるからです。夕焼けや朝焼けが赤くなるのと同じ原理です。星間赤化と星間減光との間には、関係式が成り立っています。
自分自身の重力で収縮できる星の質量程度の星間ガスのかたまりを原始星とよびます。原始星の自己重力は、収縮を妨げているガスの圧力や磁場の力よりも強いので、どんどん収縮してやがて星になります。こうして生まれたばかりの星のことを原始星とよびます。
星間空間にあるガスと宇宙塵(ダスト;固体微粒子)の雲は、星に照らされて散光星雲として見えたり、あるいは背後の星を隠して暗黒星雲として観測されます。特に密度の高いガス雲のなかでは、水素分子、一酸化炭素やより複雑な有機分子が形成されており、電波でわかる雲として観測されます。そのような雲が収縮を始めるきっかけになるものは、雲同士の衝突や近くで起こったほかの星の爆発による衝撃などです。
ガスが収縮して星になるまでの過程は数値シミュレーションによって研究されています。その結果によると、原始星は生まれるときに一時期、とても明るくなります。太陽の場合は、現在の太陽の100〜1000培の明るさで100〜1000年間くらい輝いていたと考えられています。ついで星は赤い色を保ちながら現在の太陽まで暗くなります。その後はあまり明るさを変えずに次第に黄色い星になります。
ついに星の中心で原子核反応が始まると、星は現在のような太陽の状態、すなわち主系列星に落ち着くのです。
このような原始星の収縮過程は1962年に林忠四郎氏によって提唱され、ハヤシ・フェーズと呼ばれています。オリオン大星雲のなかには,「クラインマン・ロー天体」や「ハービック・ハロー天体」と呼ばれる生まれたばかりの星が観測されています。また、ハヤシ・フェーズの終わりに近い星として『おうし座T型星』と呼ばれる種類の星があります。この種類の星は非常に若い星団のなかにある星で、まだ落ち着かずに星の表面で大規模なフレアを繰り返しています。
米国の天文学者Lynds博士によって1962年に発表された暗黒星雲のカタログです。
Lynds博士はパロマー山天文台の1.2mシュミット望遠鏡によって撮影された写真乾板をもとに、1802個の暗黒星雲を見つけ、それらの位置や広がりを記録しました。計算機が普及していなかった時代であったため、暗黒星雲の探査は全て肉眼で行われました。このため、記録された暗黒星雲のデータ(位置や広がり)の精度は低く、また暗黒星雲の基本的な物理量である減光量の測定さえ行われていません。しかしながら、Lynds博士が作成したカタログは天の北半球 を網羅しており、暗黒星雲の貴重なデータベースとして今日でも頻繁に利用されています。
パロマー山天文台(米国)およびアングロ・オーストラリア天文台(豪州)の1.2mシュミット望遠鏡によって1950年代から蓄積され続けてきた写真乾板を、高解像度スキャナーで取り込みデジタル化したデータベースです。
1541枚の写真乾板を102枚のCD-ROMに収録し、全天を網羅しています(写真乾板1枚につき、天空の6°×6°の範囲をカバー)。これは、米国の宇宙望遠鏡科学研究所によって1990年代初頭に作成されました。もともとはハッブル宇宙望遠鏡の運用のために作成されたものですが、東京学芸大の暗黒星雲探査も含めて様々な研究に広く利用されています。
2ミクロン全天サーベイは、近赤外線領域での天文観測プロジェクトです。この観測プロジェクトにはアリゾナとチリにある1.3mの口径を持つ望遠鏡2つが使われました。観測は1997年から2001年にかけて行われ、近赤外線で見た全天のデジタル画像が作られました。
この観測に用いられたのは、J(1.25 μm)、 H (1.65 μm)、 Ks (2.17 μm)という3つの近赤外線波長帯での測光データです。天の川銀河と地球との間には、莫大な量のチリやガスがあるために可視光で銀河系中心を観測することはできません。しかし、赤外線であればチリやガスを透過しやすいため、可視光では見えない部分も見えてきます。
このサイトでは、DSSと2MASSのデータを用いた暗黒星雲の姿を紹介しています。暗黒星雲を近赤外線(2MASS)と可視光(DSS)とで比べるとどのような違いがあるでしょうか。じっくりとご覧になってください。